不動産営業をしていると、お客様から「この地域の建物の高さ制限は?」と聞かれることがあります。その答えとして重要になるのが高度地区です。この記事では、不動産営業に役立つ高度地区の基礎知識を整理し、実務で活用できるポイントを解説します。
1. 高度地区とは?
高度地区とは、都市計画法に基づき建築物の高さの制限を定めた地区です。都市の景観維持や住環境の保護を目的として設定されます。特に、住宅地では日照や通風の確保、商業地では土地の有効活用などの観点から、区ごとに異なる制限が設けられています。
高度地区には大きく分けて以下の2種類があります。
| 高度地区の種類 | 特徴 | 主な用途地域 |
|---|---|---|
| 最低限度高度地区 | 一定以上の高さを確保する必要がある | 商業地域・オフィス街 |
| 最高限度高度地区 | 上限を超える建物は建築不可 | 住宅地・低層エリア |
例えば、東京都では第1種~第3種高度地区が設定されており、第1種は低層住宅地向け、第3種は商業地域向けといった形で分類されています。
2. 東京23区の高度地区の具体例
東京都では、区ごとに異なる高度地区が設定されています。主要な区の例を挙げると以下のようになります。
港区
- 斜線型高さ制限(第1種~第3種):周辺環境に応じて建物高さを制限
- 絶対高さ制限(17m~60m):ビル街と住宅地で明確な高さ規制
世田谷区
- 低層住居専用地域の厳格な高さ制限(15m~45m)
- 住宅の住環境を守るため、商業地よりも厳しめの設定
新宿区
- 駅周辺は高層建築が可能(最高限度高度地区)
- 住宅街では日照確保のため高さ制限あり
このように、区によって細かい高さ規制が異なるため、物件を紹介する際は必ず該当する地域の都市計画を確認しましょう。
3. 北側斜線制限との関係
高度地区の高さ制限だけでなく、特に住宅地では北側斜線制限にも注意が必要です。これは、北側の隣地の日照を確保するための規制で、以下のような基準があります。
- 低層住居地域:5m + 1.25 × 真北方向の水平距離
- 中高層住居地域:10m + 1.5 × 真北方向の水平距離
例えば、北側が道路の場合は規制が緩和されるケースもあるので、土地の形状や隣接関係を考慮しながら説明すると、より納得感のある提案ができます。
4. 不動産営業での活用ポイント
高度地区の知識を活用すると、物件提案の説得力が増します。以下のポイントを押さえましょう。
✅ 購入希望者向けに「この地域では高さの上限が〇〇mです」と具体的に説明
✅ 戸建て住宅の購入者には北側斜線制限も含めた日照条件を解説
✅ 投資家には、高度地区による土地の有効活用の可能性を提案
高度地区を理解し、不動産営業の知識をブラッシュアップすることで、より的確なアドバイスができるようになります。今後の商談にぜひ活かしてください!


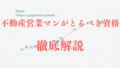
コメント